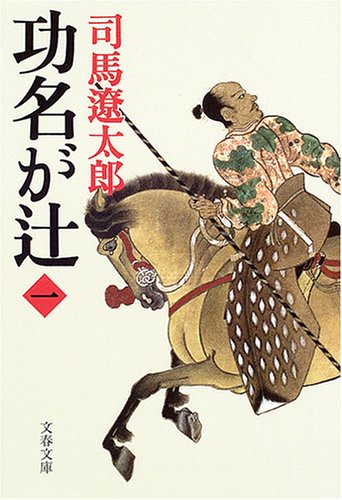山内一豊は、武将としては大きな器ではないが、妻の千代が類まれな政治センスと能力がある人で、夫を上手にたてながら陰から様々な手助けをする。
人は個々の資質を比べれば優劣が明らかになってしまうけれど、人と人との関係では、重要なのはそういう個人の資質以上に、お互いの相性なのだなあと思う。
もし一豊がもっと才能豊かな人であったり、利口な性質だったら、妻や家臣の意見など積極的に聞こうとはしなかっただろう。
そうなれば、千代のような賢妻がいたとしても、かえってそれが邪魔になって夫婦の関係はうまくいかなかったに違いない。
この作品は、山内一豊が土佐一国の大名になるまでの立身出世の物語がメインテーマだけれど、戦国時代の通史としても面白い。
数えきれないほどの武将がいた戦国時代で、信長、秀吉、家康という3人の覇者に仕えたという人は、山内一豊ただ一人しかいないのだ。
一豊の視点から戦乱の時代を見ると、その3人の性格や戦い方の違いが理解しやすいし、歴史の分岐点がどこであったかがよくわかる。
まだ、家康が勝つか負けるか定かではない関が原の合戦の時、家康に運命を託した山内一豊らの心の揺れ動く様子は、読んでいてハラハラする。
それまでの人生のすべてを賭けて、この戦いに参加しているのだ。
勝てば大名になるが、負ければ命がない。
そういう賭けのすべてに生き残ってきた一豊には、ただならぬ運もあるし、物事がよくわかる妻の意見を受け容れる度量もあった。
この作品が語っていることは、仲睦まじく助け合いながら戦国を生き抜いてきた夫婦がめでたく一国の太守になりました、という単純なストーリーではない。
もう一つ、この作品には、重要な教訓が含まれている。
物語が終わりに近づき、そのことに気がついた時には、なんと、司馬遼太郎はこれを語りたくて、ここまで長い物語を書いていたのか、と度肝をぬかれた。
物語の始めから終わりまで、一難さってまた一難が繰り返されるスリリングな展開が続き、一度読み始めたら目が離せない面白さがある小説だ。
名言
六平太、そちはさとい。わしは鈍だ。奉公は鈍なるが仕合せ、と千代も申した。これでよいと思っている。千代に言わせれば、侍奉公をする者には、無用の智というものがあるそうだ。主家と他家をくらべるという智である。この智ほど奉公を痩せさせるものはない、と千代は申した。(1巻p.274)
たしかに伊右衛門には、軽微な不運が続いていた。しかし、これを不運を思うのは愚者である、と千代は考えている。運、不運は、「事」の表裏にすぎない。裏目が出ても、すぐいいほうに翻転できる手さえ講ずれば、なんでもないことだ。(2巻p.52)
「あの、まさか一豊様は、将来かけて二万石だけでおさまっておしまいになるおつもりはございませんでしょう?」(2巻p.149)
関白秀次は、結局、吉田修理亮の「即刻決起」のすすめをしりぞけた。男ではない。と当時、一部ささやかれた。こういうときに善悪はべつとして即刻さわやかに行動できる者だけが、この当時、男という美称をうけたものである。(2巻p.328)
秀吉は古今類のない園遊会好きなだけに、その構造の雄大さ、巧みさも比類がない。遊びにも「企画力」があるのだ。千代はこの醍醐の花見をみて、つくづく(この人が天下を取ったはずだ)と思った。たとえば家康の構想力など、秀吉が月だとすればすっぽんどころか、泥がめでしかないだろう。天下取りも構想力なのである。夢と現実をとりまぜた構想をえがき、あちらを抑えこちらを持ち上げ、右はつぶして左は育て、といったぐあいに、一歩一歩実現してゆき、時至れば一気に仕上げてしまう、その基礎となるべきものは構想力である。(3巻p.122)
伊右衛門はもはや残りの春秋の多くもない生涯であるが、この最後の世の変動を機会に一国のあるじになりおおせてみたいと思っていた。(おれは太守、千代は太守夫人)という、まるで子供っぽい夢ではあったが男の生涯など、思ってみればその子供っぽい夢がかれを駆けさせる原動力になっているのではあるまいか。(4巻p.86)
(ひととは強欲なものだ)と、千代はぼんやり考えた。一代できずいた身代は一代かぎりでほろぼせばよいのに、晩年になればいよいよそれを永世にのこそうという気持ちが強く動くようであった。特に大名家業というのはそうであった。家が滅べば、家臣は禄をうしなって路頭に迷う。この家業に関するかぎり家をつづかさねば、伊右衛門の創業は成功したといえないのである。(4巻p.300)