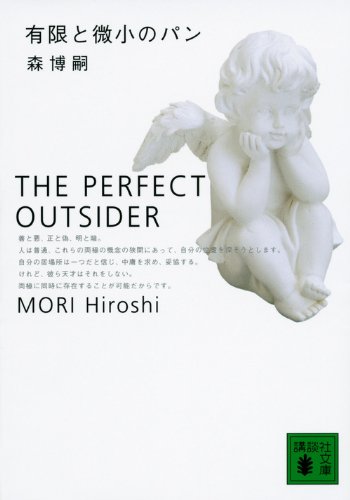シリーズ第一作目の「すべてがFになる」と対応する構造になっている、この、シリーズ最終作は、副題も、「THE PERFECT INSIDER」と「THE PERFECT OUTSIDER」で一対のものになっている。
中心のテーマになっているのは、いずれの話しも「バーチャルリアリティー(仮想現実)」。真賀田四季博士が登場することで、「生きている、死んでいる、とは何か?」のような、ある面、仏教問答のような形而上的な話しになることが多かった。犀川と真賀田四季との対話が特に面白い。
この本が書かれた当時は、まだコンピュータグラフィックスもプレイステーション1レベルのものだったのだろうから、物語の中に出てくるバーチャルシミューレーターなどは、今となるとちょっとチャチな感じがするけれども、その、「仮想」と「現実」を対比させた考察は、かなり本質的なものなので、時代に関係なく興味深い内容だと思う。
殺人事件のトリックについては、この巻の場合、かなりそちらに割り振られるウェイトも低いので、この際どうでも良かったという感じがする。
こちらの予想を超えて意表を突くところは見事な構成なのだけれど、ちょっと現実離れしすぎていて、さすがにそれは無いだろう、という感想だった。
真賀田四季には、本当に「この世にはいない」、草薙素子のような電脳世界の住人になっていて欲しかったので、ラストは、その点でちょっと期待外れ。
シリーズの締めくくりとしてはすっきりしなかったのだけれど、この後にも「四季」シリーズなどに話しが引き継がれていくことを考えれば、まだ何かがありそうな予感を残す、余韻の残る終わり方だったと思う。
S&Mシリーズというのは、犀川&萌絵のことと当たり前のように思っていたけれど、それは、犀川&真賀田、あるいは四季&萌絵の意味も含んだものであったかもしれない。いずれにしても、この3人の関係こそが、このシリーズの軸になっていたことがよくわかる巻だった。
名言
この種の電光掲示板は、人間社会のメカニズムに類似している。一つ一つの微小なライトは、ただ、ONとOFFを繰り返すだけだ。言われたとおりのインターバルで、点いたり消えたりする。つまり死ぬか生きているかを表示しているに過ぎない。それを遠くから眺めると、文字が流れているように見える。意味のあるものが読める。つまりは、これが人間の歴史ではないか。その一つ一つの単位は、自分がどんな文字の一部となったのかも知ることはない。死ぬか生きるか、しかないのである。(p.95)
彼と一緒に地下鉄に乗っていたときだ。親子の写真とともに、「パパは君で夢を見る」というキャッチコピィの広告が目についた。犀川はそれを見て、萌絵にこう言った。「子供は、あんなパパが大嫌いだ」
萌絵も同感だった。
子供で夢を見る親は、もう「親」という生きものだ。それは人間の生を放棄している。ついつい人は、そうした装飾に包まれた安楽を望むもの。(p.199)
無理をすることはない、と考えてから、「無理をする」とはどういった意味なのか、犀川はさらに考えた。無理をしないで生きている人間なんていない。生きているということと、無理をすることは、ほとんど同義なのだから。(p.378)
「我々が今感じている感覚をすべて再現しなくてはいけない、というのも正論ではありません。そんな必要はどこにもないのです。車を運転するとき、ハンドルの重さを軽減する装置がついていますよね。パワーステアリングです。あれだって、最初は、慣れないから危ないという意見がありました。しかし、反力が小さくなっても、いずれ、違和感はなくなる。そういったものだと人間が慣れてしまえば、それで良いわけです。決して今感じているものが正しいわけではない」
「コップの重さがない、という世界が?」
「そうです。自分以外の物体には重さがない、という世界を鵜呑みにできれば、それで解決です。自分がもの凄い力持ちになったと思えば良い。特に不便なことはありません」(p.505)
街が、そして建物が装飾なら、人々が着ている服だって、装飾。
そう、すべてがバーチャル・リアリティ。
「違う」萌絵は独り言を呟いた。
それどころか、人間の躰だって・・?
自分のこの躰だって・・?
装飾ではないのか?
この世界でしか動かせない手、そして足。
目と耳も、この世界でしか使えないセンサ。
思考空間では、それらは存在しない。
あのVRシステムの黒い部屋で、機械の中に自分の躰が入ったとき、
萌絵は不思議に思ったのだ。
躰が、どうして必要なのだろう、と。
自分の躰が、どうしてここにあるのだろう、と。(p.642)
「この事件全体が、博士が作ったゲームなのですか?ゲームのキャラクタだなんて、そんなのおかしいわ。私は自分で考えて行動しています」
「人の行動パターンなんて、乱数で処理できる範囲内だ」(p.659)
この部屋にいるのは、本当は真賀田四季だけなのだ。
自分たちの方が、存在しないのだ。
パンもテーブルもあるのに、自分たちはいない。
両手を持ち上げて、顔の前に掲げ、両目を覆っても、何も変わらない。
自分の手はここにはない。
目だけ、耳だけ。
視覚と聴覚だけが、ここにある。
彼女だけが存在する部屋だ。
自分は、いない。
ここには、いない。(p.754)
「バーチャル・リアリティの研究にのめり込むと、目の前の現実が有する限りない繊細さと、この上ない手軽さに対峙することになります。安価な現実と高価な虚構との対比がジレンマになる。それは、太古より人類が避けることを知らないパラドクスです。恋愛小説一作の執筆は、本物の恋愛より困難な作業としてのみ価値を見出され、風景を描写する絵画は、誰もが毎日目にする自然の美を決して超えることがない。人類の創作とは、割りが合わないゆえに、消滅を免れたといっても良いでしょう。」(p.782)
「リカーシブ・ファンクションね」四季は言った。「そう、全部、それと同じなの。外へ外へと向かえば、最後は中心に戻ってしまう。だからといって、諦めて、動くことをやめてしまうと、その瞬間に消えてしまうのです。それが生命の定義。本当に、なんて退屈な循環なのでしょう、生きているって」
「退屈ですか?」
「いいえ」四季はにっこりと微笑む。「先生・・。私、最近、いろいろな矛盾を受け入れていますのよ。不思議なくらい、これが不思議なのです。宇宙の起源のように、これが綺麗なの」
「よくわかりません」
「そう・・、それが、最後の言葉に相応しい」
「最後の言葉?」
「その言葉こそ、人類の墓標に刻まれるべき一言です。神様、よくわかりませんでした・・ってね」(p.826)