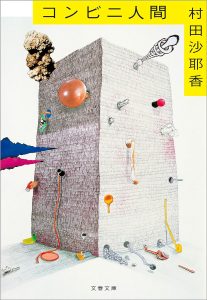面白かった。
不条理劇の雰囲気がありながら、それほど非現実的な話というわけではない。
古倉恵子は、多数派の流れに乗れない人間ではあるけれども、不幸せではないと思った。
空気を読んだり、周りに忖度をすることができない性格だからこそ、純粋な目でありのままに物事を見ることができる。
頭が悪いわけではなく、ある意味、ものすごく合理的で、無意味なことはしない、ということを自分なりに追求した結果の生活なのだと思う。
このままではいけない、と世の大勢に合わせようとしたならば、さぞかし苦しいことになるだろうと思うけれど、彼女自身は確固とした自分の世界観を持っているので、普段はそのズレを気にすることもない。
古倉恵子という人も、自然な姿からは逸脱しているかもしれないけれど、それと同じぐらいの程度で、コンビニというシステムも自然からかけ離れたものだと思う。
そして、その不自然同士の波長がぴったりと合った。
完璧なマニュアルがあって、厳密にその仕組みに則って運営されているコンビニという場は、彼女にとって、この世のどこよりも居心地が良い所なのだろう。
白羽もやはり、多数派中心の流れに乗れていない存在である点では同じだけれども、中途半端な常識と、多数派への憧れがある。覚悟が決まっていない。
古倉恵子は、今の世の中では少数派に属する人間だったとしても、将来的には、彼女のように、余計な事を考えず実直にマニュアルを厳密に運用できる人間が多数派を占めることになるのかもしれない。
過去の高度成長期には、工場のライン工のような単純作業を間違いなくおこなえる人間が重宝されて、そういう人材を大量に育てることが重視された。
コンビニの店員というのは、ライン工よりは高度で、マニュアルの範囲の中で、自発的に問題を見つけて改善していくことが求められる。
AIによって様々な仕事の内容が変わっていく中で、社会にとって必要なのは、マニュアルとシステムを作る少数の人間と、数多くの古倉恵子のような人間、である気がする。
名言
まあさぞかし生きづらいのだろうな、と思いながら、自分は白湯を飲んでいた。
味がする液体を飲む必要性をあまり感じないので、ティーバッグを入れずにお湯を飲んでいるのだ。(p.83)
妹と同じ家の中で寝ているだろう、甥っ子の姿が頭に浮かんだ。妹の人生は進んでいる。何しろ、この前までいなかった生き物がそこにいるのだ。妹も、母のように私の人生にも変化を求めているのだろうか。(p.90)
「はあ…まあ、白羽さんに収入がない限り、請求してもしょうがありませんよね。私も貧乏なので現金は無理ですが、餌を与えるんで、それを食べてもらえれば」
「餌…?」
「あ、ごめんなさい。家に動物がいるって初めてなので、ペットのような気がして」(p.102)
私は泣いている妹に尋ねた。
「じゃあ、私は店員をやめれば治るの?やっていた方が治ってるの?白羽さんを家から追い出したほうが治るの?置いておいたほうが治ってるの?ねえ、指示をくれればわたしはどうだっていいんだよ。ちゃんと的確に教えてよ」
「もう、何もわからないよ…」
妹は泣きじゃくり、返事をくれることはなかった。(p.123)
18年間、辞めていく人を何人か見ていたが、あっという間にその隙間は埋まってしまう。自分がいなくなった場所もあっという間に補完され、コンビニは明日からも同じように回転していくんだろうなと思う。(p.133)
何を基準に自分の身体を動かしていいのかわからなくなっていた。今までは、働いていない時間も、私の身体はコンビニのものだった。健康的に働くために眠り、体調を整え、栄養を摂る。それも私の仕事のうちだった。(p.138)
私の遺伝子は、うっかりどこかに残さないように気を付けて寿命まで運んで、ちゃんと死ぬときに処分しよう。そう決意する一方で、途方に暮れてもいた。それは解ったが、そのときまで私は何をして過ごせばいいのだろう。(p.142)
「身体の中にコンビニの『声』が流れてきて、止まらないんです。私はこの声を聴くために生まれてきたんです」
「なにを…」
白羽さんが怯えてような表情になり、私は畳み掛けた。
「気が付いたんです。私は人間である以上にコンビニ店員なんです。人間としていびつでも、たとえ食べて行けなくてのたれ死んでも、そのことから逃れられないんです。私の細胞全部が、コンビニのために存在しているんです」(p.149)