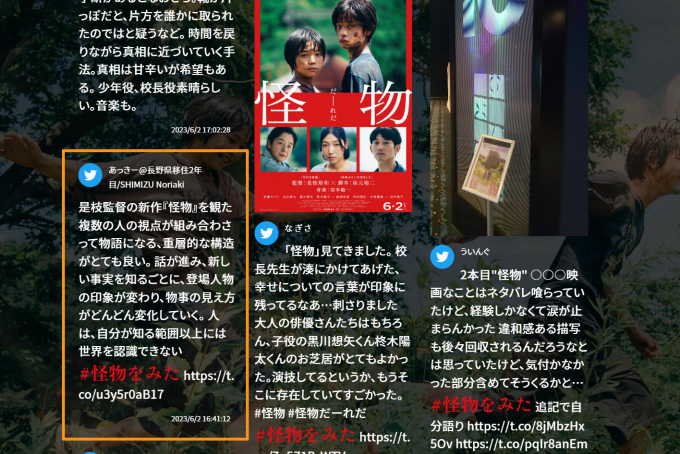是枝裕和監督作品が好きなので、公開初日の朝、一番最初の上映回で観てきた。
複数の人たちの視点が組み合わさって物語を作り出す、重層的な構造が、とても良かった。
おそらく2回目を観た時は、初回とまったく印象が変わるだろう。
映画の舞台が諏訪湖畔の街、というところも良かった。
そして、子どもたちの年齢が小学校5年生というところも、同年代の子を持つ親として共感を持つことがあり、親の役割や、担任、学校の役割について考えさせられた。
(※この先はネタバレを多く含みますので、ご自身で観る予定がある方は、ここで離脱することをオススメします)

見え方が変わっていく登場人物
一番驚いたのは、担任の保利先生のキャラクターの見え方が、途中から一変したこと。

最初の登場の時は、コミュニケーションを成立させることができない、どうやってこのヒトが学校の先生になれたんだ?と思わせるレベルのヤバい奴に見えた。
しかしそれは、母親の視点からのみ見た時の姿で、実際に母親からはこの通りに見えているのだろうけれども、実態はそう単純ではないことがわかってくる。
そして、映画の作り方としても、このミスリードを意図的に演出している。
最初、母親が知り得る情報のみを見せ、母親の心情と一致させて、母親から見える息子の姿、学校の姿を、観客に見せている。
他の登場人物についても、物語が進むに連れて、新しい情報が開示されるごとに、どんどんと見え方が変わっていく。
校長先生の変化もスゴい。
孫が死んだショックで痴呆か認知症でも始まっているのかと思いきや、わかっていないフリをしているだけで、実際にはかなり計算高く、状況を把握していることがわかる。
そうなると、2年生の時の担任だったという神崎先生も、正体があやふやになってくる。
母親は、「素晴らしい先生でした。だから、この学校の先生全員が悪い人ではないと思います」と言っているけれども、それがどれだけ正当な評価なのか、その後、画面の端々に登場する彼の言動を見ていると、虚実がわからなくなってくる。
同じ人間を見ていても、その人について知っている面によって、ここまで印象が変わるものなのかと驚かされる。
しかし、考えてみれば、現実世界もこれと同じようなもので、自分が見ている世界は、自分が知り得た範囲の中で解釈したものでしかない。
物事の見え方は、関わった人の数と同じだけあるはずなのだけれど、その全体を俯瞰して見ることができるのは天上の神の視点だけ。
その視点を与えてくれるのが、この作品の一番面白い点だった。
生きにくい同士が惹かれ合う
シングルマザーの家庭で育つ少年と、シングルファーザーの家庭で育つ少年。
そういう環境にあることに加えて、マイノリティーな特性を持つことで、生きにくさを抱えることになる。

ヨリくんのことを「病気」だと父親は言っていたけれど、何のことを指して病気と言っているのか、最初わからなかった。
はじめのうちは軽度の知的障害なのかと思った。
作文で鏡文字を書いていることから、読み書きにも困難があるのかと。
同性愛の傾向がある、というのは完全に予想外だった。
「え!?そういうことだったの?」と。
その設定だと、物語の解釈が結構変わってきてしまうから、そこは、そういう設定にはしてほしくなかった、と個人的には思う。
それが理由で、母親にも父親にも見棄てられるなんて、あるだろうか。
純粋に、少年同士の友情にしておいてほしかった、という気持ちだ。

同じ場面の、別のアングル
この映画は、物語の時系列を何度も入れ替えることで、出てきた伏線の種明かしをすることがよくあった。
同じ時間の同じ場面を映したものなのだけれど、別のアングルから見ると、今までは見えていなかったものが見えてくる。
湊が教室で暴れたのは何故だったのか。
それを言葉で表現するのではなく、ただ、場面のアングルを変えることで示す。
過剰に説明的でない、この手法はとても好きだ。

街で火事があったその時間のことは、何度も登場する。
最初は湊が見た火事の画。その後に、保利から見た火事、校長先生から見た火事。
それぞれの人間に、それぞれが感じた、違う意味がある。
保利先生が、屋上の屋根に登って、諏訪湖の方面に向かって立つシーンがあった。
この時、屋上から飛び降りようとしていたのか、そうじゃないのかは、わからない。
ただ、この時、背景にはトロンボーンの音が聴こえていた。
湊が校長先生に自分の本心を告白をした時ということだ。
そのこととシンクロしたのであれば、彼もその時、何かに触発をされて、新たにやり直そうと思ったのかもしれない。

最後までよくわからないままだった謎もあった。
校長が学校に残ることにこだわったのは何故なのか?
湊と依里が、口を揃えて嘘をついて、担任の保利を陥れたのは何故だったのか。
どうして、そうしないと秘密がバレることになるのか、理屈がよくわからなかった。
保利が何気なく口にした「男らしくないぞ」という軽口が気に障ったのかも、とは思った。
そして、「怪物」とは結局何だったか、というのは観終わった後もあまりピンときていない。
一番怪物っぽかったのは、中村獅童演じる依里の父親と、校長先生か。
この点は、ちょっとタイトルが思わせぶりすぎなんじゃないか、という気がしている。
田中裕子の言葉の重み
校長先生の言葉は名言だった。
「そんなの、しょうもない。誰かにしか手に入らないものは幸せって言わない。しょうもないしょうもない。」
誰にでも手に入るものを幸せと言うのだ、と。
これは、涙が出たな。

誰だって、どんな人間だって、今すぐに幸せになれる。
幸せはなるものではなく、感じるものだ。
校長先生の、達観した雰囲気。
すべてを諦めたようでいながら、現状維持に執着する欲深さ。
子どもが大好きで、大嫌い。
アンビバレントな多面性が一人の中に潜んでいる。
一言では言い表せない、かなりの深みのある人生観を持っているのだろうと思う。
この役を田中裕子がやっているというのが、またいい。
彼女の口から発せられると、言葉の重みが違う。

それにしても、孫娘を誤って轢き殺してしまった、というエピソードはインパクトが強すぎて、とても気になるところなのだけれど、詳細はよくわからないままだった。
拘置所にいる夫に面会に行って、話す内容が「お骨を入れる墓は別になった」とかいう話で、今する話か?というところなど、何かがズレてて怖い。
人間の多面性を感じられる映画
永山瑛太が演じる保利先生も、いいキャラクターだったな。
「ストーカーみたいで、笑顔が気持ち悪い」と周りに言われていて、実際そんな感じに見えてしまうのだけれど、単に不器用で空気が読めなかったり空回りしているだけで、芯のところでは純朴な人間。

安藤サクラ演じる麦野早織は、子どもを守ることに必死な母親であり、それは間違いないのだけれど、途中から自分の正義を通すために、ためらいなく辛辣な言葉を投げつけるようになり、学校を相手取って徹底抗戦をするモンスターのようになった。

死んだ夫のことは良い思い出として語り継いでいるけれども、それもどこまでが本当なのかわからない。
湊に対して望む、普通に結婚をして家庭を持つ、という平凡なはずの幸せ像が、湊にとっては大きな負い目になってしまう。
「僕はお父さんのようにはなれない」と。
湊にしても、被害者のように見え、加害者のように見え、実際のところ、どちらの姿も持ち合わせていた。
とにかく、登場人物のイメージが、話が進むに従って、刻々と変わっていく映画であった。
最後まで変わらなかったのは、星川依里くらいか。
湊がさらっと、父親が死んだのは、愛人と温泉旅行に行って事故死したからだ、と依里に言っていた。
残された母親の語る様子からすると、立派な父親だったのかと思いきや、そうでもなかったらしい。
或いはもしかしたら、その事実を知っているのは湊だけで、胸の内に一人で抱えているのかもしれない。
本当に、つくづく、人間の中に潜む多面性を感じさせる映画だった。